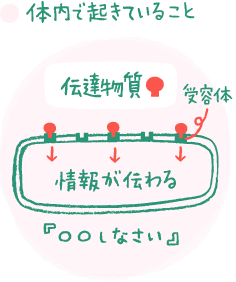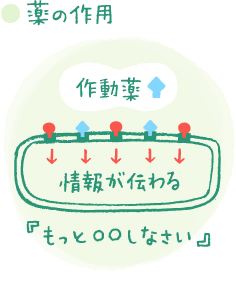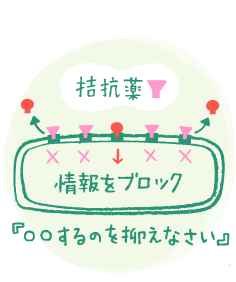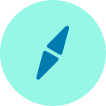
薬が作用する仕組み。受容体とは。
薬が作用する仕組み Vol.1

気になる症状を改善し、からだを楽にしてくれる薬って、からだの中で何か特別なことをしているはず。そう思っていませんか?ところが、多くの薬は新しい作用を引き起こしているわけではありません。もともとからだの中で起きている作用を、強めたり弱めたりすることで、気になる症状を改善します。
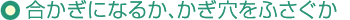
では、薬はどのようにして、本来からだが持っている働きを強めたり弱めたりしているのでしょうか……。ターゲットは、細胞にある指令の受け口、「受容体」です。もともとからだの中には、細胞に指令を伝えるさまざまな「伝達物質」があり、それらが受容体と結合することで「○○しなさい」という指令が細胞に伝わります。それはまるで、「かぎ」と「かぎ穴」のような関係で、ピッタリ合うときだけ指令が伝わるのです。
薬はこの仕組みを利用しています。“合かぎ”となり、かぎ穴にピッタリ入って、「もっと○○しなさい」とからだの働きを促す薬を「作動薬」、伝達物質が受容体にくっつくのを邪魔して、「○○するのを抑えなさい」と、からだの働きをブロックする薬を「拮抗薬」と呼びます。


不足している作用を強くする薬の例
ぜんそくの薬:ぜんそくの発作がおこらないように気道(気管支)を拡げる
抗うつ薬:脳の働きをコントロールする物質の不足を補う
強すぎる作用を抑える薬の例
抗アレルギー薬:アレルギーのもとになる物質(ヒスタミン)が作用するのを抑える
降圧薬:血圧を上げるために、血管を収縮させる物質ができるのを抑える
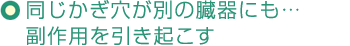
薬は、口から飲んだり皮膚に塗ったりしたあと、血液によって全身をめぐります。その際、別の臓器の細胞に同じ形のかぎ穴(受容体)がある、というのも実はよくあること。そのため、薬を作用させたい場所とは異なる場所の細胞に薬が作用してしまうことがあります。
たとえば花粉症の症状を抑えるために使う抗ヒスタミン薬。鼻水や目のかゆみを引き起こす「ヒスタミン」が、鼻や目の細胞にあるヒスタミン受容体にくっつかないように邪魔をして症状を抑えます。ところが、ヒスタミンの受容体は脳の細胞にもあります。ヒスタミンは覚醒や集中力アップに必要な物質でもあるので、脳の細胞でのヒスタミンの作用が抑えられると、眠気の副作用が生じます。
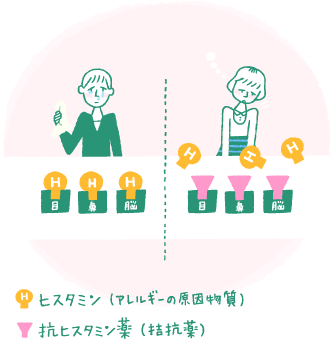

どのような薬も、効かせたい部分にだけ薬が作用し、効かせたくない部分にはなるべく作用しないようにするための研究が進められています。
花粉症の薬では、眠気の副作用が起こりにくいように、脳に行きにくくした薬も出ています。

薬の多くは受容体に作用することで効き目を発揮しますが、別の所に作用するタイプの薬もあります。いずれにしても、さまざまな細胞や体内物質に働きかけて、正常な状態を取り戻すのを助けてくれるのが薬です。
参考:中嶋敏勝編著:疾病の成り立ちと回復の促進
薬理学 医歯薬出版:33-44, 2005

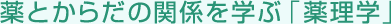
薬とからだが、どんな風にかかわりあっているのか研究する学問を「薬理学」って呼ぶよ。
薬理学は、薬を飲む。薬の入口とその種類 からだを旅する薬のことで取り上げた、薬がからだの中でどのような運命をたどるのかを知る「薬物動態」と、今回から3回に分けて勉強する、薬がからだにどんなふうに作用するのかを知る「薬力学」が2本柱なんだ。
薬が効く仕組みを知るには、この2つがとても大切。からだの中で何が起きているのかを知るために、薬を正しく使うために、そして新しい薬を創り出すためにも、欠かせない学問だよ。

参考:赤池昭紀、石井邦雄編集:最新薬理学 廣川書店:1, 2012

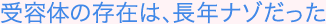
薬が作用するのに欠かせない「受容体」。今では当たり前の存在のように考えられていますが、実際に、受容体が次々と見つかったのは、ほんの40~50年前、1970年代でした。
そこからさかのぼること約70年。「きっとあるはず」と最初に目を付けたのは、イギリスのラングレイ(John Newport Langley)という研究者です。1905年に発表した論文の中で、「受容体物質(receptor substance)」という考え方を提唱しました。
ラングレイは、中南米原産のヤボランジという植物の樹皮や葉に含まれるピロカルピンという物質の研究をしていました。ヤボランジをかむと、だ液の分泌が促されることが知られていて、その仕組みを解明しようとしていたのです。
研究を続けるうちに、チョウセンアサガオやベラドンナという植物に含まれるアトロピンという物質には、ピロカルピンとは正反対の、だ液の分泌を抑える作用があることに気付きました。
そこでラングレイは、「ピロカルピンとアトロピンは、同じところに作用して逆の反応を引き起こすのではないか、その作用点となる受容体があるはず」と考えたのです。
約70年もの間、仮想的な存在だった受容体。からだの中で起きるさまざまな現象、そして薬が作用するのに必要不可欠な、生命の根幹にかかわる働きをしています。
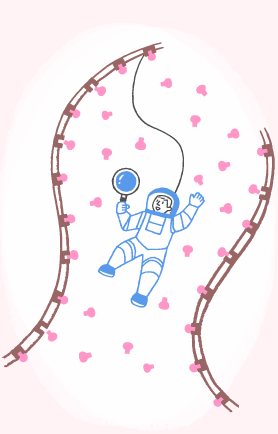
参考:Maehle AH:Medical History 48(2):153-74, 2004

監修:加藤哲太(日本くすり教育研究所代表)