
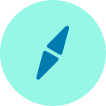
学校スマイル応援プロジェクトVol.2
ー震災復興支援ー2013
震災復興支援 学校スマイル応援プロジェクト
被災した子どもたちをサポートして
未来へつなぐ
「学校スマイル応援プロジェクト」は、東日本大震災で被災した子どもたちのための教育活動に懸命に取り組んでいる学校を支援するプロジェクトです。住友ファーマはこのプロジェクトに2011年6月から参加して、被災した子どもたちのための運動会や職業体験学習など、様々な学校行事を積極的にサポートし、次世代の育成支援に取り組んでいます。
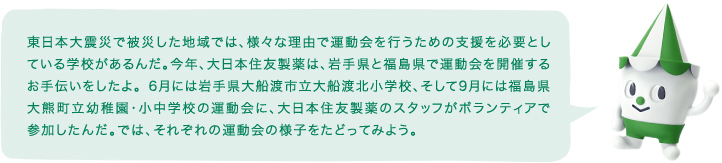
2013年6月
岩手県大船渡市立 大船渡北小学校運動会
他校の校庭で開催した運動会
6月1日、大船渡市立大船渡北小学校の運動会が、となりの学区にある大船渡小学校で開催されました。大船渡北小学校をはじめとして、大船渡市内の多くの小・中学校には、現在も仮設住宅が建設されており、運動会や体育の授業を行う場所がありません。そのため、大船渡市立大船渡北小学校では、仮設住宅のない大船渡小学校の校庭を借りて、運動会を開催しました。



普段は校庭が使えず、競技の練習することもなかなかできない状況でしたが、児童たちはのびのびと元気いっぱいの演技を見せてくれました。
子どもたちがいきいきとしていて、応援している保護者や先生たちも、とてもうれしそうでした。

運動会の最後の演目では、5・6年生合同による「赤澤鎧剣舞(あかさわよろいけんばい)」が披露されました。この剣舞は、大船渡に何百年も受け継がれている伝統の舞です。子どもたちの力強い踊りに、地域の保存会の方々による太鼓演奏も加わり、大迫力の演技となりました。
昔から伝わる伝統の舞だから、地域の方々もみんな知っていて、太鼓の音に合わせて舞が始まった瞬間、会場がひとつになったのを感じました。
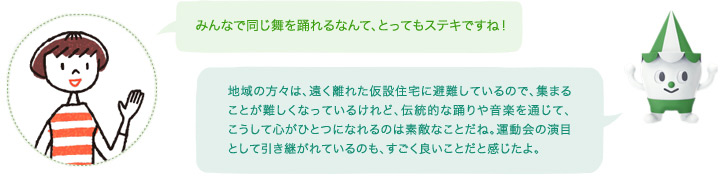
2013年9月
福島県双葉郡大熊町立幼稚園・小中学校合同運動会
避難先で迎えた、3回目の合同運動会
大熊町の幼稚園・小中学校合同の運動会「顔晴(がんば)ろう!大熊っ子!大会」が9月14日、会津若松市河東町(かわひがしまち)の大熊町立小学校(熊町・大野小学校)で開催されました。
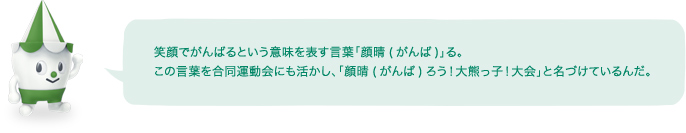
この運動会は2011年、2012年に引き続き、今年で3回目となり、343人の児童・生徒が参加し、住友ファーマからは10名のスタッフがお手伝いしました。運動会当日の朝は、曇り空でしたが、開会式が始まる頃には真っ青に晴れ渡り、子どもたちは気持ちのいい青空の下で練習の成果を思う存分に発揮していました。この運動会の演技や競技には様々なアイデアが取り入れられ、会場を大いに盛り上げました。演技や競技に取り組む子どもたちの顔はとても輝いて見え、参加した方々の顔からも笑顔がこぼれていました。大熊町の方や保護者、お世話になっている河東地区の方々(※)など、たくさんの皆さんに、日ごろの感謝の気持ちを、子どもたちの「笑顔と元気な姿」で伝えることができました。
※福島第一原子力発電所の事故により、大熊町の皆さんには2011年3月12日に全町避難命令が出されました。
そのような状況のなか、避難先の会津若松市の多大な協力により、廃校舎などを活用して、大熊町の幼稚園と小中学校の移設が実現しました。


大熊町の子どもたちや先生方、保護者や親戚の方々以外にも、大熊町から避難されている方、避難先の会津若松市の方、他の地域に転居された方など、大勢が集まり、子どもたちを応援していました。集まったみんなの応援は、きっと子どもたちに届いていたと思います。




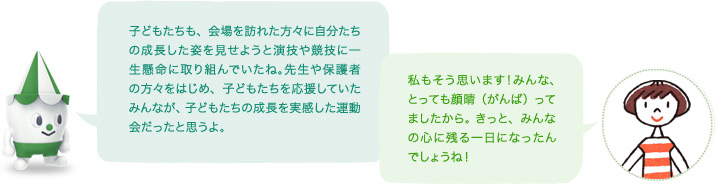
心に残る一日を支えるために
大熊町の宝である子どもたちが活躍する合同運動会は、保護者や先生方にとっても大切な行事です。そして、大熊町の子どもたちが互いに助け合いながら「顔晴(がんば)」っていこうという気持ちを奮い立たせる場になるだけでなく、子どもたちを受け入れ学校生活を再開する環境づくりに協力するなど物心両面から支援されている会津若松の方々への感謝の場でもあります。
そうした大熊町の方々の想いを陰ながら支えるために住友ファーマのスタッフも、運動会の実施をお手伝いしました。


住友ファーマのスタッフは、自動車で来られた方を駐車場に誘導したり、駐車場内の車両整理をしたり、運動会の会場から離れた場所で働いていました。
参加したスタッフは、「私たちは地域の方々に楽しい時間を過ごしてもらいたい、笑顔あふれる運動会を届けたいとの思いをもって、この活動に参加しています」と話していました。また、「私たちが関わったのはわずか1日でしたが、笑顔で帰られる皆さんの姿を見て、本当に良かったと感じました。」といった感想ももらいました。
いろいろな人の力や想いが一つになって、素晴らしい運動会ができました。
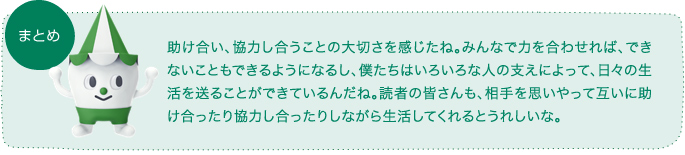
まとめ
助け合い、協力し合うことの大切さを感じたね。みんなで力を合わせれば、できないこともできるようになるし、僕たちはいろいろな人の支えによって、日々の生活を送ることができているんだね。読者の皆さんも、相手を思いやって互いに助け合ったり協力し合ったりしながら生活してくれるとうれしいな。






